| 詩吟は詩の意味も、情趣も、声によって表現されますが、 カラオケでのような美声はいりません。 丹田からうまれる、清朗豪快な味のある声(修練による)がふさわしいですね。 低い老声(寂びごえ)も、また一味あります。 親からもらった自分の声の良しあしを気にすることはないですね。 漢詩には■七言絶句■五言絶句■律詩■古詩 ■新体詩 といったものがあります。 句の配列には一定の法則があります。 絶句を例にとれば ■七言絶句は起承転結で構成されてます。
詩の文体をよくみて、詩の内容を理解し、起承転結にも注意して、その詩にふさわ しい節回し(節調)で吟じることが大切ですね。
最近、詩吟では「CD」の伴奏で吟じることが多く5線譜(5音階)の譜付けがされます が、本来詩吟では、上音、平音、下音と三音階でよばれてました。 言葉(詩)の部分はアクセントと抑揚で感情を表し、余韻をもたせる声(節調)として 平声、上声、去声、入声の「四声」がもちいられます。 その変化と、速度の緩急などによって節回し(節調・旋律)が生まれます。 詩を上手く吟じるには余韻、抑揚、緩急が必要ですね。 最近、コンクールでは、「CD」伴奏が主流なりましたが ほとんどが1分50秒~1分55秒以内の構成です。 *各流派に沿った伴奏ばかりではありません。 *コンクールにでるときは「CD」伴奏に合った吟題を選ぶことがたいせつです。 ■四声[しせい] 平声[ひょうせい/ひょうしょう](長くひくが、高低の変化はない) 上声[じょうせい/じょうしょう](長く引いて終わりが高くなる) 去声[きょせい/きょしょう](長く引いて終わりを低く落とす)) 入声[にゅうせい/にっしょう](低くはじまり、高くなって、ふるわせながら落とす) 平声のことは「平字」ともいい、「○」で表示します。上声、去声、 入声の三つを合せて仄声[そくせい]または仄字[そくじ]といい、 「・」で表示します。 ■平仄法[ひょうそくほう] ■七言絶句・起承転結[しちごんぜっく・きしょうてんけつ] ■平起式七言絶句[ひょうきしきしちごんぜっく] ■仄起式七言絶句[そくきしちごんぜっく] ■二四不同[にしふどう] ■二六同[にろくどう] ■押韻[おういん] ■一三五不論[いちさんごふろん] ■下三連を忌む[かさんれんをいむ] ■詩語集[しごしゅう] |
|||||||||||
| 漢詩って2 | |||||||||||
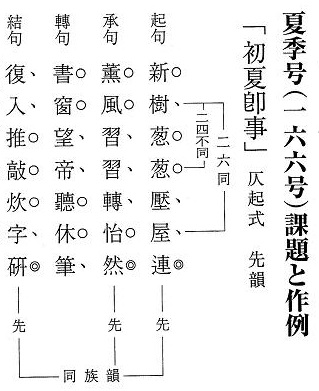 関西吟詩文化協会ホームページより |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| 詩吟を始めよう ◇声って ◇声ってどうして出るの① ◇声ってどうして出るの② ◇腹式呼吸って ◇基本形 ◇五線譜をなぞるだけ ◇漢詩って 一歩リード ◇無声音とは |