 |
|
一品二魄三節四声 一に品格、二に魄迫、三に節調、四に声力 詩吟の奥義である品格を求めて、謙虚に日々生きて行こうと思う今日この頃であります 好きな詩吟をうたいながらわいわいがやがや。。。。。 面白く 楽しく をモットーにに集まってます |
|
構成吟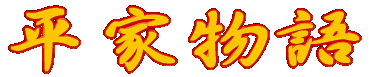
日本六十余州の大半を領し、「平家に非ずんば人に非ず」とまで嘯きし平家、 その権力は、天皇と結びつき、 娘・徳子が生んだ、後の安徳天皇がその繁栄の証とも言うべき存在でありました。 安徳天皇誕生と即位と言う、まさに平家繁栄の全盛期 わが世の春を謳歌したのです。・・・・・・・・しかし 幾多の人間ドラマが交差しながら 源平、あい乱れる争乱の幕が切って落とされ、 日本の歴史上、稀な海戦という形で 壇ノ浦の戦いがクライマックスを迎えます。 ここに源平にまつわる漢詩・和歌に耳を傾けてみようではありませんか。 構成吟「平家物語」の開幕は、平家一門の栄華とその没落、滅亡を描く 祇園精舎 平家物語より 常盤は耐え忍んだ。命こそ、この命こそ和子たちをまもるものと・・・・。 ここで、その雪中さまよう親子の様子を詠んだ詩をお聞きください。 常盤弧を抱くの図に題す 梁川星巌 太政大臣になた清盛は祇王という白拍子を寵愛したが ある日訪れた都一番の舞上手と評判の白拍子仏御前の美しさに すっかり心を奪われた。 とうとう祇王に暇を与えてしまった。 祇王は黒髪を断ち切り、浮世への未練をも断ち切った。 祇王の立ち去った館の襖障子には、祇王が涙で綴った次の和歌が記されていた。 萌え出づるも 祇王 平治の乱で敗れた源義朝を父とし、常盤を母として、平治の合戦中に産声をあげた それからといううものは、平家憎しの思いは募るばかりであった。 16歳になった牛若、まだ明けやらぬ早暁、奥州の藤原秀衡のもとへ、 安徳天皇が即位され、平家全盛の世となったが・・やがて 平治の合戦以後20年間の忍の一字を破り平家打倒の旗が掲げられた。 やがてこれより、数年にわたる源平争覇の時代へとつながるのである。 倶梨伽羅 朝日将軍木曽義仲 一の谷懐古 梁川星巌 泊壇ノ浦 木下犀潭 かけて知る 安徳天皇 壇ノ浦懐古 安積艮齋 壇ノ浦を過ぐ 村上仏山 清盛の妻二位尼に抱かれた幼い帝は、「波の下にも都のさぶろうぞ」と言う 鎌倉幕府の平家追討軍に選ばれた那須大八郎宗久が、険しい山脈に分け入り、 稗つき節 栄華の夢も打ち捨て、わずかに露の命をつなぐこの有様。それでも猶、 |
